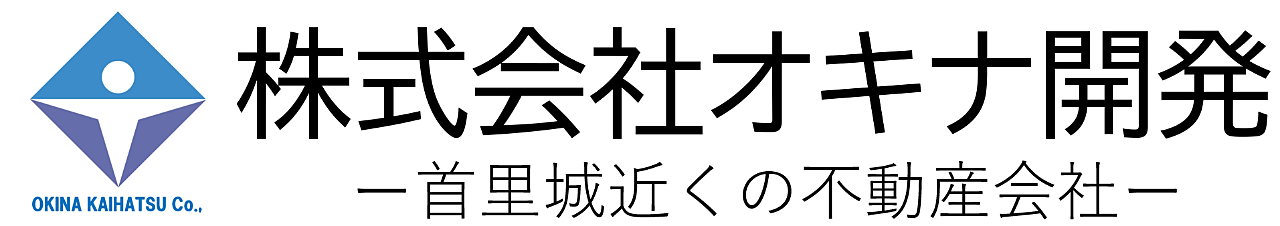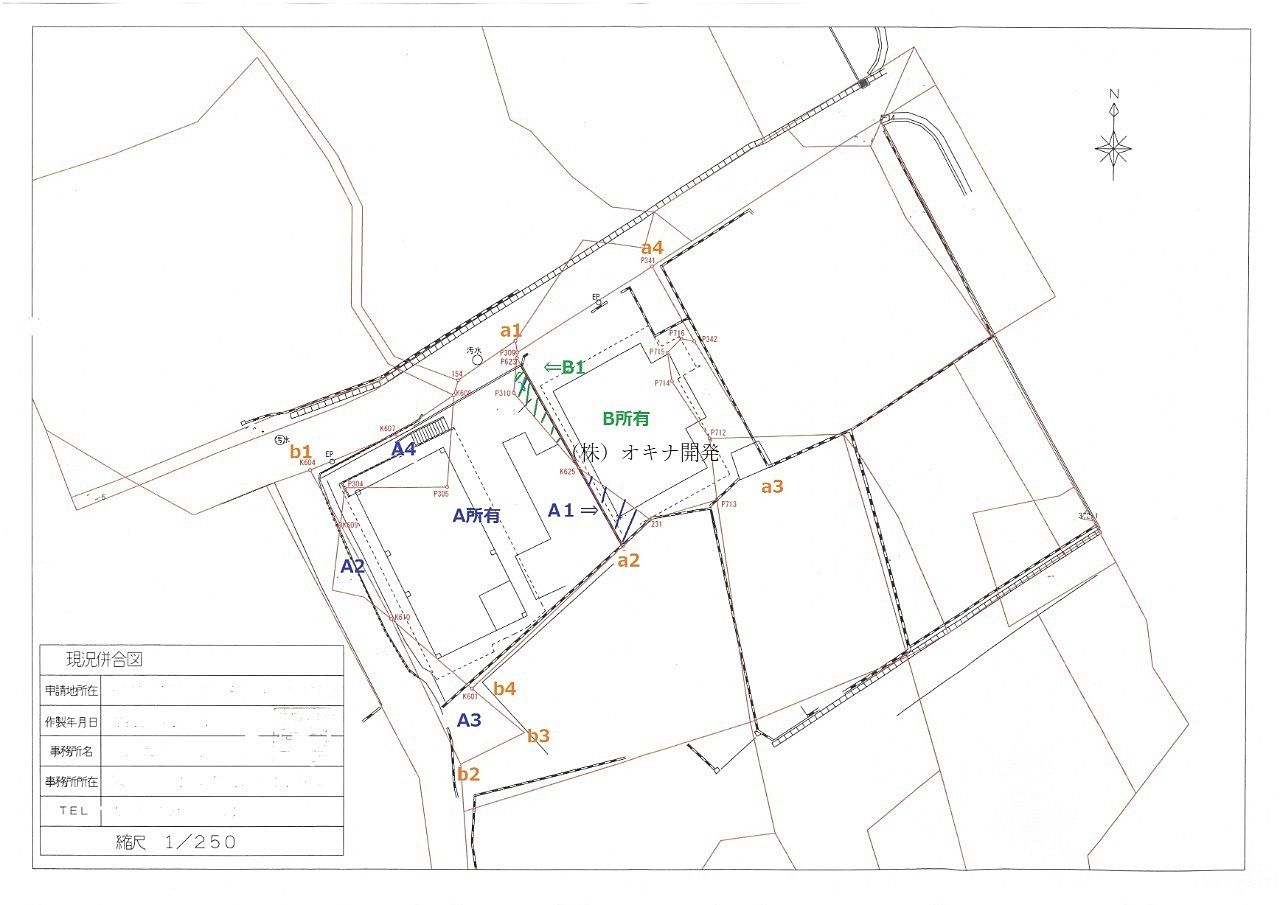杭を残して、悔いを残さず
今日のタイトル
土地家屋調査士業界の標語のようなもので
グットネーミング賞をあげたいくらいです(笑
グッジョブ!と言いたくなりますね
相隣関係とは・・・?
法律上の境界(筆界)と現況は一致しないこともあります
さて、見にくいかもしれませんが
上の図をご覧ください(クリックすると拡大します)
赤い線が法律上の境界で筆界と言います
見る限り越境のオンパレードです
Aさんが所有する土地を売却する為調査したところ
公図と現況が一致しないことは一目瞭然でした
A地もB地も現所有者は相続で取得したもので
過去の経緯は知らず、親御さんから土地に関することは
何も聞いていないとの事で
お互いに越境していることを知りませんでした
これから土地家屋調査士と共同で作業にはいります
上記図面は現況併合図と言いますが
法務局に備え付けられた地図に
建物や塀など現況を落とし込んだ図面で
まだ境界は確定していません。
A地とB地の間にあるオレンジ色a1~a2にはブロック塀があり
AさんBさんともブロック塀が境界との認識でした
ところが、測量するとBさんの土地にAさんの土地が入り
Aさんの土地にが入り互いに越境している事が分かりました
またAさんの土地はA2とA3
それぞれ他人所有の私道と隣接地に入り込んでいることが判明しました
ここからが私の仕事です
A地とB地間の越境A1とB1はほぼ面積も同じ
3.5坪と3.7坪で許容範囲
等価交換で金銭のやりとりは無しで
測量費を按分しご負担頂くことで解決
Aさんの登記上の所有権は
大まかに言うと
a1からb1 b2 b3 b4 a2 を結ぶ赤い線です
私道に越境しているA2
私道の所有者を探す調査を開始
近くではありますが近隣ではありません
車で15分ほどの所に住んでおり相続で取得していましたが
30年以上も前のことで
自分名義の土地があることをすっかり忘れていました
その方の考えをお聞きしたところ
持っていても使いようがないからと
安価で譲って頂くことになりました
問題は後ろの越境部分です
白と黒で引かれた線は隣地との境に設置されたブロック塀等です
一般的にはブロック塀が境界との認識です
A3は隣地の庭部分に白黒ブロック塀から約6メートル
不整形ですが最大で横3メートル程度入り込んでいます
面積にすると5坪に満たないくらいですが
このような状況では決して小さい面積ではありません
これが大都会なら億単位の大問題です
色々と頭の中でシュミレーションしながら
お宅へ土地家屋調査士同行で説明に伺いました
そちらの方はA地の元所有者である現所有者の親と
昔、仲が良かったらしく
現所有者を幼いころから知っている様で
穏やかに懐かしそうに話しを聞いて頂きました
今回は売主、B地所有者、私道の所有者、
後方隣地のA3を庭として占有している土地の所有者
皆さん穏やかな方々で揉めることなく話は進んでいきました
皆さん、平穏かつ公然に、
間違いなく所有の意思を持って占有していますので
互いに時効取得を援用すれば
ほぼ間違いなく認められると思います
A地の売主さんもA3を相場で買ってもらうのではなく
いくぶんか測量費を負担してくれれば譲っていいとの事でしたので
それぞれ面積で測量費を按分してもらうことで
解決した珍しい事例でした
一般的に境界がズレている場合
どちらかが建替える際に境界に沿って塀を作り直すと
合意書を取り交わし相続や売買で
所有者が変わっても合意書は承継されるとし
ほぼ現状維持ですが(しばらく越境状態が続く)
互いに問題があることを共有することが大切です
今回の場合、地形が不整形で四方八方が互いに入り込んでおり
問題を先送りせず、
権利関係を正しくしたほうが良いと判断しました
区画整理地や開発された所は
このような問題が起こる事は少ないですが
30年以上前から住んでいる地域等は認識している境界とズレがある
場合があることを認識しておいたほうが良いと思います
当社の所在する首里地域は国が地積調査を行い立会も完了してるので
境界は確定済みです。
因みに、杭や標は隣接する所有者の立会が無いと設置できません
立会を終えるとは隣地所有者に承諾が得られた事を示しますが
承諾が得られない場合は杭や標を設置できなく境界未確定となります。
関連した記事を読む
- 2025/05/19
- 2025/05/17
- 2025/05/16
- 2025/05/12